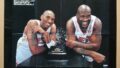87-NBAオールスター2009
2009年のオールスターは“入れ替わり”の合図だった
2009年・フェニックス。あの一夜は、ただの祭りじゃない。ロスターの顔ぶれを眺めると、世代交代、チーム作りの最適解、そして「現役No.1」をめぐる物語が一気に立ち上がった年だったと分かる。
「デビン・ハリスが移籍で開花」「レブロンの隣でモー・ウィリアムズが躍動」「ラシャード・ルイスとジャミーア・ネルソンのマジックが東をかき回す」。この断片をつなぐと、当時のリーグがどこへ向かっていたかがくっきり見える。
デビン・ハリス—“スピードの価値”が通貨になった瞬間
ダラスからニュージャージーへ。トレードを機に、デビン・ハリスは一気に花開いた。
ポイントは「役割の再定義」。ダラス時代はテンポ管理とオフボールの比率が高かったのに対し、ネッツではハイピックからギア全開で縦に割るドライバーとして起点になる比率が一気に増えた。
結果、
- フリースローで点を稼ぐ“軽量スコアラー”へ変貌
- スペースが空けば pull-up(止まって打つジャンパー)で確実に刻む
- 終盤のクラッチ場面も迷いが消え、コートを「まっすぐ」切り裂く判断が増えた
当時のリーグはまだ“ポジション伝統論”の残り香が強かったけど、ハリスの成功は「PGでもいい、サイズが足りなくてもいい。スピード×FT獲得×ミドルの止め打ちでオフェンスを成立させられる」という合図になった。彼のオールスター選出は、“スピードが資産”である時代に本気で舵が切られた証明でもある。
モー・ウィリアムズ—レブロンの隣に置くべき“第2のハブ”
レブロンの隣で光ったのがモー・ウィリアムズ。
求められたのは「ボールを預けても良し、預けなくても良し」。レブロン起点の5アウト(もしくは4アウト1イン)で、モーは
- スペーサーとしてコーナー&45度で幅を出す
- セカンドピック&ロールのハンドラーとして攻め筋を増やす
- 速攻の2次波で pull-up 3 を差し込む
彼の“待てるPG”としての性質は、ボールを持つ時間の長いレブロンと噛み合った。数字以上に大きかったのは心理的効果で、「レブロンが休んでも、コートは暗くならない」とチーム全体に思わせたこと。
その結果としてのオールスター招集(たとえ代替選出であっても)は象徴的だった。**“レブロンの相棒”の定義が、ボールを長く持つスターではなく、**起点にも終点にもなれる“ハブ型ガード”だと広く共有されたからだ。
マジックの解—ラシャード×ジャミーア×ドワイトで作った“4アウト1イン”
オーランドの快進撃を支えたのが、ラシャード・ルイスとジャミーア・ネルソン。
- ラシャード・ルイス:本職SFの射程をそのままPFに持ち込むズレ。相手のビッグマンを3Pラインまで連れ出し、ドワイトのダイブとリムランのレーンを開ける。いわば“ストレッチ4”の完成形のひとつ。
- ジャミーア・ネルソン:小さくても強い。ピックの使い方が巧みで、エルボーへ運んでからのフロート、コーナーへのキックアウト、そしてテンポチェンジ。AS前の負傷は痛恨だったけど、**「小さくても効率で殴る」**という当時の潮流を体現していた。
ドワイトを真ん中に据えた“4アウト1イン”は、
- リム周りの圧を最大化(ロブ、セカンドチャンス)
- 3Pで揺さぶる(HedoのP&R、ラシャードのトレイル3)
- 相手の2本柱をいずれか一方は外へ引きずり出す
という三段構え。2009年のマジックは、**「リムと3点で勝つ」**という後のリーグ標準を東でいち早く形にしていた。
オールスターという“鏡”—Kobe & Shaq 共同MVPの意味
試合そのものもドラマがあった。西の勝利、そしてコービーとシャックの共同MVP。
かつての相棒が一夜限りに並び立ち、肩を並べて笑う。単なるノスタルジーじゃない。「支配の仕方が変わっても、天才は文脈を跨いで物語を作る」—その再確認だった。
この夜、フェニックスのコートは二つの時間軸が重ね合わさっていた。レイカーズ三連覇の記憶と、スモール×スペーシングへ向かう新時代の足音。そこにハリス、モー、ラシャード、ジャミーアといった“新解答”の面々が肩を並べたことに、このオールスターの価値がある。
「現役No.1」論争—レブロン初MVPで輪郭がはっきりした
2008-09のレギュラーシーズンMVPはレブロン。
ここから「現役No.1=レブロン」が声として大きくなっていく。理由は明快で、
- 万能性の過剰:トランジションのエンジン、ハーフコートの司令塔、そしてエンドゲームの決定力。
- 守備の証明:サイズと脚力で1~4番に跨るスイッチ守備、ヘルプの読みも深い。
- 勝ちの再現性:レギュラーシーズンでの支配が、コアメンバーの入れ替えがあっても揺らがない。
一方でこの論争は、**“ファイナルの文脈”**が常に引き合いに出される宿命にあった。
「シーズンを支配する力」と「最後の4勝をもぎ取る力」が必ずしも一致しないからだ。ここに2009~2010のレイカーズが割って入る。
コービーの“起死回生”—08の悔しさを、09と10で上書きする
2008年、ボストンに叩きのめされたファイナル。そこで突きつけられたのは、**“個の超越と構造の強度をどう両立するか”**という問いだった。
翌シーズン、レイカーズは答えを持って帰ってくる。
- ガソルの軸足:ハイポストのフェイスアップ、ローポストの両手フィニッシュ、ショートロールのハンドオフ。攻撃のつなぎ目を作り、コービーの難度をコントロール。
- オドムの流動性:4番運用でのプッシュ、ペリメータでの受け渡し、ロングリバウンド回収。
- 守備の徹底:フィル・ジャクソンが“長身ウイングの壁でPA内を狭める。
そしてファイナルMVP。翌2010年も含めた2連覇で、コービーは“シャックとなしでも勝てる”を改めて刻印する。
ここが「現役No.1」論争の肝だ。レギュラーシーズンの圧=レブロン、プレーオフでの価値=コービーという二項対立が、以後の10年代初頭のNBA言説を温め続ける。
「この頃のレイカーズの2連覇はコービーにとって起死回生」—まさにその通りで、08年の記憶を塗り替え、“個の美学”と“組織の強度”を同居させた答えを提示した。
2009年が教えたチームビルディング
この年のオールスターと、その後のプレーオフ含む流れは、チーム作りの要点を3つに要約できる。
- スター×ハブの両立:モーのような“第2の起点”が、ボール支配の重いエースを救う。
- ストレッチの正義:ラシャード型のストレッチ4は、強いリムプロテクター(ドワイト)と相性が極めて良い。
- テンポとFTの価値:ハリスが示したように、スピードと笛の管理で効率は底上げできる。
この3つは、その後の10年代のリーグ標準になっていく。2010年代の王者たちは、程度の差はあれど全部これを踏まえている。
オールスターは人気投票の側面が強いけど、この年の顔触れは戦術トレンドと勝利のロジックをかなり誠実に反映していた。だからこそ、今見返しても学びが多い。
総括:物語は交差し、王道は更新される
2009年は“交差点”だ。
コービーとシャックの記憶、レブロンという新王の即位、マジックの戦術革新、そして役割を得て伸びた面々。
この交差点をレイカーズの2連覇が駆け抜け、Kobeのレガシーは起死回生する。
あの年のオールスターを起点に、リーグは**「リムと3点」「スター×ハブ」「ストレッチ4」**へと加速。
そして「現役No.1」をめぐる論争は、シーズンの支配とファイナルの決定力という二つの物差しで語られるようになった。
—2009年を語ることは、NBAの“王道がどう更新されたか”を語ること。だからこそ、今もなお面白い。
・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓
・その他の投稿がコチラ↓