63-ドワイト・ハワード
ドワイト・ハワードという男──支配者としてのピークと過小評価の実態
1年目から即戦力、未来のリーグを背負うと評された男
2004年NBAドラフト全体1位指名。この一言が、ドワイト・ハワードの期待値のすべてを物語っていた。高校卒業即プロ入り、そして1年目から全82試合に出場。平均12.0得点・10.0リバウンドという成績で、ルーキーながらダブルダブルを叩き出したその存在感は、まさに“即戦力”だった。
だが、ハワードの価値は得点ではない。インサイドでのリバウンド、ブロック、ヘルプディフェンス、スクリーナーとしての貢献と、数字に表れにくい部分でもチームに絶対的な存在感を与えていた。センターというポジションに必要な要素を、すべて高水準で満たしていた数少ない選手。それが若き日のドワイト・ハワードだった。
ディフェンスの権化、DPOY3年連続受賞の衝撃
ハワードを語る上で外せないのが、守備力だ。2008-09、2009-10、2010-11の史上初の3年連続でNBA最優秀守備選手賞(DPOY)を受賞。
リムプロテクトにおける反応速度、タイミング、跳躍力。すべてが一流。特に2.9ブロックを記録した2009年、彼の守備範囲は“ゴール下”ではなく“ペイントエリア全域”だった。ドライブで突っ込めばハワード、ポストで仕掛けてもハワード。相手チームのオフェンスプランを根本から破壊する存在として、リーグ全体に恐れられた。
08-09シーズン、最高潮の頂点へ
ドワイト・ハワードのキャリアにおいて、最も輝いたのが2008-09シーズン。個人成績としては20.6得点・13.8リバウンド・2.9ブロック。数字だけでも驚異的だが、それ以上にインパクトが大きかったのがプレーオフでの活躍だった。
イースタン・カンファレンスファイナルでは、当時MVPだったレブロン・ジェームズ率いるキャブスを相手にシリーズ平均25.8得点・13.0リバウンド・1.2ブロックというモンスタースタッツを記録。ファウルゲームを仕掛けられるも、重要な局面で苦手とされたフリースローを沈め、キャブスの作戦をことごとく打ち砕いた。
マジックをNBAファイナルへと導いたこの活躍は、“チームの柱としてファイナル進出”という重みを持ち、他のレジェンドセンターたちと並んでも見劣りしない偉業だと言える。
変遷するチーム、失われた主役の座
2012年、レイカーズ移籍──ここからハワードのキャリアは迷走を始める。コービー・ブライアント、スティーブ・ナッシュ、パウ・ガソルと並んだドリームチームのような布陣も、現実はケミストリーに苦しみ失敗。ハワード自身も背中の怪我に苦しみ、ロサンゼルスでの1年目は失望に終わる。
その後はヒューストン・ロケッツ、アトランタ・ホークス、シャーロット・ホーネッツ、ワシントン・ウィザーズなど、次々にチームを渡り歩くジャーニーマンとなった。特にジェームズ・ハーデンとの共存に失敗したロケッツ時代は象徴的で、ボールを要求する機会が減り、オフェンスの主軸ではなくなる中で評価も下落していった。
だが、これはハワードのパフォーマンスが急落したからではない。NBAの潮流が、インサイドの支配者からアウトサイドのスモールラインナップへと劇的に変化していった時代背景もある。彼は“時代の転換点”に翻弄された存在ともいえる。
キャリア全体で見たとき、ハワードはどこまでの選手だったか?
ドワイト・ハワードの通算スタッツを見てみよう。
- 通算リバウンド:14,627(歴代10位前後)
- 通算ブロック:2,228(歴代20位前後)
- 通算得点:19,000点超
- オールNBAチーム選出:8回(うちファーストチーム5回)
- DPOY:3回
- オールスター出場:8回
- リバウンド王:5回
- ブロック王:2回
- 2020年にはレイカーズで優勝(ロールプレイヤーとして)
スタッツと実績を見れば、センターとして歴代でもトップ10クラスと評価されるべき実績を残している。彼は“攻守両面における支配力”を持った数少ないセンターの一人であり、特に守備においては歴代でも屈指の存在だった。
75周年チームに非選出、そして浮かぶ違和感
2021年、NBA75周年を記念して発表された「NBA 75周年記念チーム(選出されたのは76人)」に、ドワイト・ハワードの名はなかった。この選出には多くのバスケットボールファン、そして元選手たちも疑問を呈した。
アンソニー・デイビスのように、キャリアの途中でもうすでに選ばれた選手もいる中、キャリア通算でハワードの方が実績で上回っているという声は根強い。「全盛期の勢い」はあっても、「継続性」や「ディフェンスでの支配力」「ファイナル進出」などを見れば、ハワードの方が上とする意見も多い。
もちろん人格的な側面や、チームメイトとの軋轢といったイメージ面のマイナスも影響した可能性はあるが、それにしても“実績”がこれほどある選手を選出しないことの違和感は拭えない。
ドワイト・ハワードは「時代を背負ったセンター」だった
ハワードが全盛期を迎えた2000年代後半から2010年代初頭は、NBAにおける“最後のインサイド支配時代”だったとも言える。ペイントを守り、リムを支配し、フィジカルで勝つ。ハワードはその象徴であり、センター像の最終形だった。
確かに、シュートレンジは狭く、パスセンスも限られていた。だが、それを補って余りあるほどのフィジカルとディフェンスの支配力。1on1で勝負してくるレブロンを止め、苦手とされるフリースローでシリーズの流れを決める。そんな舞台で勝負を決められるセンターは、そう多くはない。
ドワイト・ハワードは、“勝者”ではなかったかもしれない。だが、“支配者”ではあった。勝利が届かなくても、その選手が「リーグの顔」だった時期があるならば、それは一つの正当な評価として刻まれるべきだろう。
・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓
・その他の投稿がコチラ↓
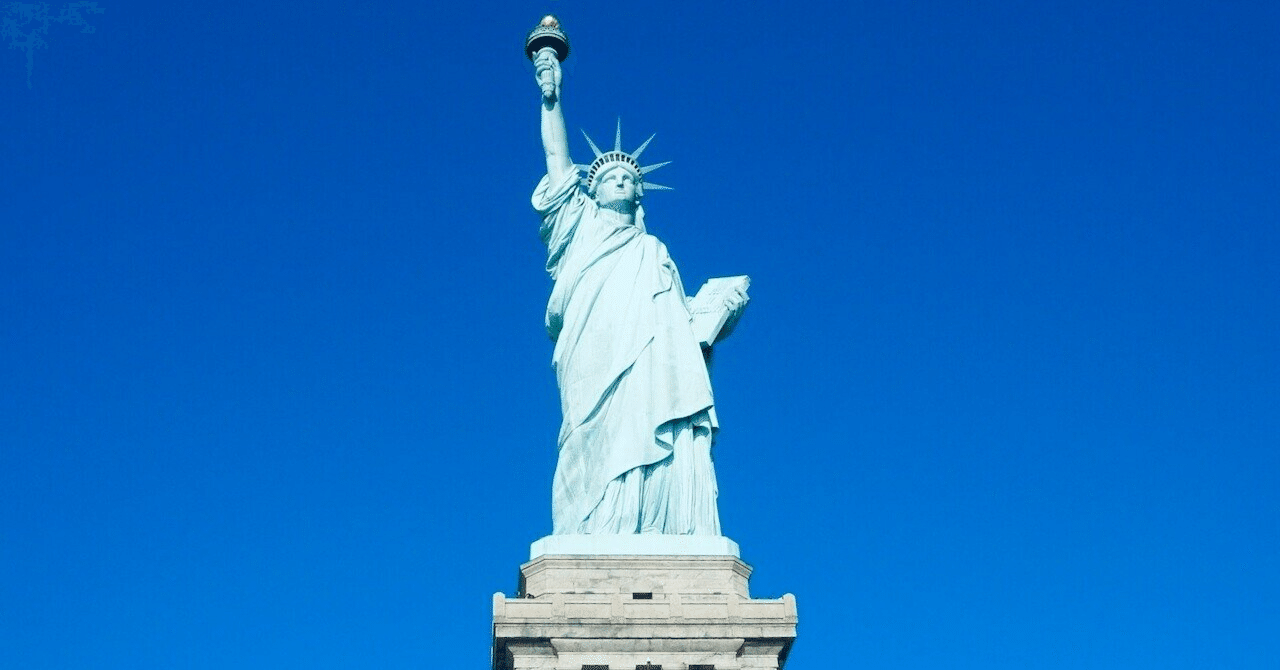



コメント