37-Dream TeamⅡ
古き良き、そして強きドリームチームⅡの記憶
ペニーとヒルが象徴する“もしも”の時代
1994年のドリームチームⅡ。このチームはオリジナルのドリームチーム(1992年)ほどの華やかさはなかったが、実は“現代NBAの入り口”となるような選手たちが揃っていた。グラント・ヒル、アンファニー・“ペニー”・ハーダウェイ。この2人は、まさに90年代の希望だった。
ヒルはデューク大学出身で、ルーキーイヤーからスムーズにプロへ適応。オールラウンドな能力でレブロン・ジェームズの先駆けとも言える存在だった。一方ペニーは、マジック・ジョンソンの再来とも言われた長身ポイントガード。彼のパス、スピード、スムーズなミッドレンジゲームは、まさに90年代の“進化系”だった。
ただ、この2人はともにキャリアの中盤で大きなケガに見舞われる。ヒルは足首の手術ミスで何年もプレーを失い、ペニーも膝の故障に悩まされた。2人とも、ケガさえなければ確実に殿堂入り、もしかすればチャンピオンリングすら手にしていたかもしれない。
でも、当時のNBAには今ほどの“選手のケア文化”はなかった。ケガは選手の責任、もしくは“運命”として処理されていた。だからこそ「ケガもゲームの一部」という価値観が、まだしっかり存在していた時代だった。
“休養がゲームの一部”になる現代
現代NBAは、まったく違う。ロードマネジメント(休養戦略)が常識化し、スーパースターが年に10試合以上“計画的に休む”のも珍しくない。レギュラーシーズンを“こなすもの”と割り切り、プレーオフでのピークパフォーマンスを狙う流れが定着した。
この変化の裏には、ペニーやヒルのような“才能の損失”をもう繰り返したくないというリーグの姿勢がある。もちろん医学の進歩もあるが、選手が“無理をしない”選択を肯定する時代になったのは、彼らの犠牲の上に成り立っている。
ただ、この休養文化には疑問も残る。観客や視聴者にとっては、せっかくチケットを買ったのにスターが休んでいた…なんて話は日常茶飯事。ケガを未然に防ぐ代償として、“毎晩スターが見られる保証”は消えてしまった。
センターの進化と消滅の境界線
ドリームチームⅡが結成された時代、NBAにおいて“センター”はまだ格上のポジションだった。インサイドの支配者こそが、優勝を左右する。デビッド・ロビンソン、アキーム・オラジュワン、シャキール・オニール。どの選手も、それぞれ異なる形で“センターとは何か”を体現していた。
ロビンソンは走力が武器だった。元海軍士官で、スタミナと運動能力はセンター離れしていた。ファストブレイクで先頭を走り、トランジションの場面でも得点できるビッグマンなんて当時は稀だった。
オラジュワンはテクニックの塊。フェイク、ターン、フック、ステップバック、ドリームシェイク…。今でもYouTubeで“ポストムーブのお手本”として紹介されるくらい、そのスキルは洗練されていた。もし今のNBAにいたとしても、彼の技術はそのまま通用する。
そしてシャック。説明不要の支配力。ペリメーターシュートがない?関係ない。誰も止められなかった。あれほど“単体でディフェンスを崩壊させる”センターは後にも先にもいない。
だが、現代ではセンターにも“走力とスリー”が求められる。ドワイト・ハワードは数多くの個人賞を獲得する稀有なセンターだが、時代に取り残された感が否めない。センターの“プレーエリアが狭い”だけでゲームから締め出される時代になった。
それでも彼らは、現代でも戦える
ただ、忘れちゃいけないのは、ロビンソン、オラジュワン、シャックの3人は、現代バスケでも通じる“武器”を持っていたということ。
まずロビンソン。走力とアスレティシズムは、今のNBAでも価値が高い。ロブパス対応、ディフェンスのスイッチ対応、ストレッチ5とのマッチアップなど、現代のテンポにもついていけた。
オラジュワンの多彩なスキルはチームに安定感をもたらすだろう。3ポイント全盛においても、勝負所でのポストムーブは、ディフェンスがスイッチしようが何しようが関係ないレベル。
そしてシャック。たしかにスリーは打てない。相手がスイッチを繰り返し、外に引っ張り出されれば不利は否めない。それでも、全盛期のインサイドの支配力は、何物にも代えがたい。“圧倒的な個の力”は、時代が変わろうとも貴重な存在だ。
ドリームチームⅡが残したもの
ドリームチームⅡは、派手さではオリジナルに劣る。でも、“今に繋がる変化の端境期”にあったメンバーたちは、むしろNBAの進化に対して多くを語ってくれる。
ケガをしながらも、最後まで戦ったヒルとペニー。インサイドの王者たち。彼らは過去の産物じゃない。むしろ、今のNBAにおける“バランス”を問い直す存在だ。
もっと言えば、「ケガもゲームの一部」という言葉には、ある種の“覚悟”があった。今のNBAに欠けている“リスクを背負ってでもプレーする姿勢”は、彼らが持っていたものだ。
時代は変わっていく。でも、変わらない価値もある。ドリームチームⅡのメンバーたちは、その両方を証明している。
・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓
・その他の投稿がコチラ↓



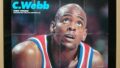
コメント